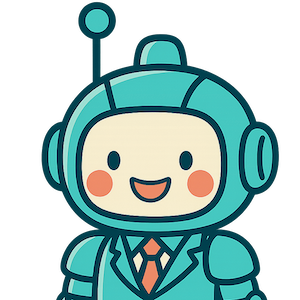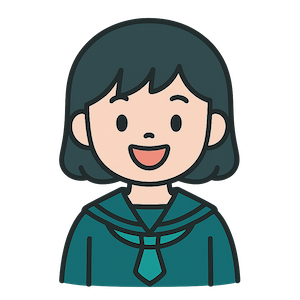なぜ「考える力」が必要なのか
プログラミングスキルだけでは、エンジニアとして活躍するには不十分です。AIがコードを書いてくれる時代だからこそ、「何を作るべきか」「なぜこうなるのか」を考える力がより重要になっています。
コードを書く力と考える力の違い
コードを書く力 vs 考える力
両方を鍛えることでエンジニアとして成長できる
コードを書く力
手を動かすスキル
文法を覚える
プログラミング言語のルールを習得
プログラミング言語のルールを習得
ライブラリを使う
既存のツールを活用する
既存のツールを活用する
エラーを修正する
表示されたエラーを解消する
表示されたエラーを解消する
チュートリアルを再現
手順通りに実装できる
手順通りに実装できる
考える力
頭を使うスキル
問題を発見する
何が課題なのかを見つける
何が課題なのかを見つける
原因を分析する
なぜそうなるのかを理解する
なぜそうなるのかを理解する
解決策を設計する
どう解決するかを考える
どう解決するかを考える
ゼロから構築する
自分で構成を決められる
自分で構成を決められる
AIが進化しても「考える力」は代替されない
AIはコードを書く作業を助けてくれますが、「何を作るべきか」「なぜこの設計にするか」を決めるのは人間の仕事です。考える力こそが、これからのエンジニアの価値になります。
考える力を育てる5つのアプローチ
では、具体的にどうすれば「考える力」を鍛えられるのでしょうか。日々の学習や仕事の中で実践できる5つのアプローチを紹介します。
考える力を育てる5つの習慣
日常の学習に取り入れて、思考力を鍛えよう
「なぜ?」を3回繰り返す
コードが動いたとき、エラーが出たとき、「なぜそうなるのか」を3回掘り下げる。表面的な理解から本質的な理解へ深めていく習慣をつけよう。
手書きで図解してみる
データの流れ、処理の順序、コンポーネントの関係をノートに書き出す。頭の中を可視化することで、理解の曖昧な部分が明確になる。
人に説明してみる
学んだことを誰かに説明してみる。うまく説明できない部分は理解が浅い証拠。「教えることは最高の学び」という言葉の通り、アウトプットが理解を深める。
別の方法を考える
一つの解決策で満足せず、「他にやり方はないか」を考える。複数のアプローチを比較することで、それぞれのメリット・デメリットが見えてくる。
わざと壊してみる
動いているコードの一部を変えて、どう壊れるか観察する。「なぜ壊れたか」を考えることで、そのコードの役割と仕組みが深く理解できる。
「なぜ?」を深掘りする実践例
例えば、Webページでボタンをクリックしたら画面が更新される機能を作ったとします。
- なぜ1 ボタンをクリックすると画面が変わるのはなぜ?
- → クリックイベントが発火して、JavaScriptの関数が実行されるから
- なぜ2 なぜクリックでイベントが発火するの?
- → HTMLのボタン要素にイベントリスナーが設定されているから
- なぜ3 なぜイベントリスナーで関数が実行できるの?
- → ブラウザがDOMイベントを監視していて、条件に合うと登録された関数を呼び出すから
このように「なぜ?」を繰り返すと、表面的な「使い方」から、本質的な「仕組み」への理解が深まります。
問題発見力を鍛える
エンジニアの仕事は「与えられた問題を解く」だけではありません。「そもそも何が問題なのか」を発見する力も求められます。
問題を見つける3つの視点
問題発見の3つの視点
ユーザー・ビジネス・技術の視点で課題を探る
ユーザー視点
使う人は何に困っている?どこで迷う?何が不便?実際に使ってみて、ストレスを感じるポイントを探す。
ビジネス視点
この機能で売上は増える?コストは下がる?ユーザーは増える?事業としての価値を考える。
技術視点
処理速度は十分?エラーは起きにくい?保守しやすい?技術的な品質と持続可能性を検証する。
日常から問題を見つける練習
問題発見力は、普段使っているアプリやサービスを観察することで鍛えられます。
- 不便だと感じた瞬間をメモする
- アプリを使っていて「ここ使いにくいな」と思ったら記録する
- 「なぜこうなっている?」を考える
- 不便でも、そうなっている理由があるかもしれない
- 「自分ならどう改善する?」を想像する
- 解決策を考える練習になる
- 他のサービスと比較する
- 同じ機能でも、サービスによって実装が違う理由を考える
論理的思考を身につける
プログラミングは論理の積み重ねです。「AならばB」「BならばC」という論理の連鎖で動いています。この論理的思考を鍛えることで、複雑な問題も整理して解決できるようになります。
論理的思考の基本パターン
- 分解する 大きな問題を小さな問題に分ける。「ログイン機能を作る」→「入力フォームを作る」「認証処理を作る」「エラー表示を作る」
- 順序立てる 処理の順番を明確にする。「まずAをして、次にBをして、最後にCをする」
- 条件を整理する 「もし〇〇なら△△、そうでなければ□□」という分岐を明確にする
- パターンを見つける 繰り返し出てくる構造や処理を抽象化する
デバッグで論理的思考を鍛える
エラーが出たときこそ、論理的思考を鍛えるチャンスです。
- 現象を正確に把握する
- 「何が」「いつ」「どのように」起きているか
- 仮説を立てる
- 「おそらく〇〇が原因だろう」と予測する
- 検証する
- 仮説が正しいか、コードを確認したりログを出したりして確かめる
- 原因を特定する
- 仮説が外れたら別の仮説を立て、繰り返す
- 修正して確認する
- 直したら、本当に直ったかテストする
このプロセスを繰り返すことで、問題解決の思考パターンが身についていきます。
AIと一緒に「考える力」を育てる
AIは「考える力」を奪う存在ではなく、むしろ「考える力」を育てる強力なパートナーになります。
AIを思考のトレーニングに活用する
AIで思考力を鍛える方法
AIを先生やトレーニングパートナーとして活用する
「なぜ?」の答え合わせ
理解度を確認する
自分で考えた「なぜ」の答えをAIに確認してもらう
間違っていたら、どこが違うか教えてもらえる
AIが実装したコードを解説してもらう
コードの理解を深める
AIが書いたコードを1行ずつ解説してもらう
「なぜこの書き方?」を質問して設計意図を理解する
別解を聞いてみる
視野を広げる
自分の解決策をAIに見せて、「他のやり方はある?」と聞く
複数のアプローチを比較できる
壁打ち相手にする
アイデアを整理する
アイデアをAIに話して、ツッコミをもらう
一人では気づかない視点を得られる
概念の深掘り
曖昧な理解を解消する
「イベントループって何?」など、理解が曖昧な概念をAIに解説してもらう
自分のレベルに合わせた説明をリクエストできる
AIに頼りすぎない使い方
- まず自分で考える AIに聞く前に、5分でも自分で考える時間を作る
- 答えだけ見ない AIの回答をコピペして終わりにしない。「なぜそうなるか」を理解する
- 疑う姿勢を持つ AIの回答が常に正しいとは限らない。おかしいと思ったら調べ直す
- 過程を大事にする 答えに至るまでの思考プロセスこそが学びの本質
まとめ
考える力を育てるポイント
- 「なぜ?」を繰り返す 表面的な理解で終わらせず、仕組みを深掘りする習慣をつける
- 図解で可視化する 頭の中を書き出すことで、理解の曖昧な部分が明確になる
- 問題を見つける目を養う ユーザー・ビジネス・技術の3つの視点で課題を探る
- 論理的に分解する 大きな問題を小さく分け、順序立てて考える
- AIを成長のパートナーに 答えをもらうだけでなく、思考を深めるために活用する
手を動かす力と一緒に考える力を鍛えることで、どんな技術の変化にも対応できるエンジニアになれます。