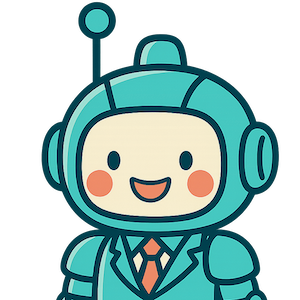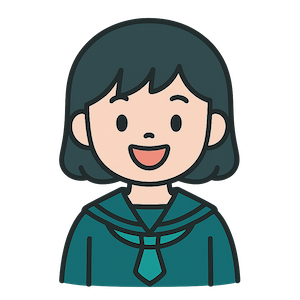Webアプリ開発の基本的な流れ
Webアプリケーションを作るプロセスは、大きく分けて以下のような段階を踏みます。プロジェクトの規模や開発手法によって詳細は異なりますが、基本的な構造は同じです。
この流れは、どんなに小さなプロジェクトでも、大規模なシステムでも基本的には同じです。ただし、実際の開発では一直線に進むのではなく、各段階を行き来しながら進めることが多いです。
開発の進め方には大きく分けて2つのアプローチがあります。
- ウォーターフォール型
- 各工程を順番に進めていく方法です。要件定義→設計→開発→テスト→リリースと、段階を踏んで進みます。変更が少ないプロジェクトや、大規模なシステム開発に向いています。
- アジャイル型
- 小さな単位で「計画→開発→テスト」を繰り返し、少しずつ機能を追加していく方法です。要件が変わりやすいプロジェクトや、スタートアップの開発に向いています。
フリーランスとして働く場合、どちらの開発手法で進めるかは、プロジェクトやチームによって異なります。両方の特徴を理解しておくことが大切です。
フリーランスが実際に関わる範囲
フリーランスエンジニアが関わる典型的な範囲
- 企画・要件定義 ほとんど関わらない。クライアント企業が社内で決定済みのことが多い(プロジェクト管理する前提で案件に参画しているなら関わる)
- 外部設計 関わる機会は少ない。システム全体の構成は決まっていることが多い
- 内部設計 ここから参加することが多い。画面設計やデータベース設計を担当
- 開発 最も頻繁に関わる部分。フロントエンドまたはバックエンドの実装を担当
- テスト 自分が実装した機能のテストを担当。単体テスト〜結合テストまで
- 公開・運用 初期リリースまでは関わるが、長期運用は別の体制になることが多い
それでは、各工程の内容を詳しく見ていきましょう。フリーランスとしてどう関わることが多いかも合わせて解説します。
企画・要件定義:何を作るかを決める
プロジェクトの最初のステップは、何を作るかを明確にすることです。この段階では、クライアントや関係者と話し合い、アプリに必要な機能やターゲットユーザー、解決したい課題を整理します。
この段階で決めること
- 目的とゴール このアプリで何を実現したいのか、どんな問題を解決するのか
- ターゲットユーザー 誰が使うアプリなのか、どんな人を想定しているか
- 主要機能 必須の機能と、あると嬉しい機能の優先順位
- 制約条件 予算、納期、技術的な制限などの前提条件
この段階でAIを活用すると、要望の整理やアイデアの具体化がスムーズになります。例えば、ChatGPTやClaudeに「こんなアプリを作りたい」と相談すると、必要な機能のリストアップや、似たサービスの事例を提示してくれます。
「ECサイトで中古の本を売買できるサービスを作りたい。必要な機能をリストアップしてください」のように具体的に聞くと、ユーザー登録、商品登録、検索、決済、レビュー機能など、必要な要素を漏れなく提案してくれます。
設計:どう作るかを決める
要件が決まったら、次はどう作るかを設計します。この段階では、画面のレイアウト、データの構造、システム全体の構成などを考えます。
設計で作るもの
設計は大きく外部設計(システム全体の構成や画面・操作に関する設計)と内部設計(具体的な実装の設計)に分かれます。開発系エンジニアとしてのフリーランスは、主に内部設計を担当することが多いです。
(小規模・フロントエンド案件では担当も)
外部設計:システム全体の構成と仕様
外部設計では、システム全体の枠組みや、ユーザーから見える部分の仕様を決めます。
システム全体の構成等は主にプロジェクトリーダーやデザイナーが担当し、フリーランスエンジニアは既に決まった方針の中で作業することが多いです。
ただ小規模案件や特にフロントエンドエンジニアとして参画する場合は、画面設計から任されることも珍しくありません。
- システム構成設計
- フロントエンド、バックエンド、データベース、外部サービスなど、システム全体をどう構成するかを決めます。どんな技術を使うか、サーバーはどこに置くかなども、この段階で検討します。
- 画面設計(UI設計)
- どんな画面が必要で、各画面にどんな要素を配置するかを決めます。ワイヤーフレームと呼ばれる簡単なスケッチを描くことが多いです。
FigmaやAdobe XDなどのデザインツールを使うこともありますし、紙とペンで簡単にスケッチすることもあります。最近では、AIを使って画面のモックアップを自動生成することもできます。
- どんな画面が必要で、各画面にどんな要素を配置するかを決めます。ワイヤーフレームと呼ばれる簡単なスケッチを描くことが多いです。
内部設計:実装の詳細を決める
内部設計では、外部設計で決まった仕様をどう実装するか、具体的な設計を行います。この段階から開発系フリーランスが積極的に関わることが多く、技術的な知識と経験が求められます。
- データ設計(DB設計)
- どんなデータを扱い、それをどう保存するかを決めます。例えば、ユーザー情報、商品情報、注文履歴など、必要なデータの種類とその関係性を整理します。
- 詳細設計
- クラス設計、API仕様、処理フローなど、実際のコードを書く前の最終的な設計を行います。どのような関数やメソッドが必要か、データの流れはどうなるかなど、開発者が実装に移れるレベルまで詳細化します。
この設計があることで、チーム内で実装方針が統一され、効率的に開発を進めることができます。
開発:実際にコードを書く
設計が終わったら、いよいよ開発段階に入ります。この段階では、設計書をもとに実際のコードを書き、機能を実装していきます。
フロントエンドとバックエンドの開発
Webアプリ開発は、大きくフロントエンド(ユーザーが見る画面側)とバックエンド(サーバー側の処理)に分かれます。
フロントエンド開発
HTML、CSS、JavaScriptを使って、ユーザーが実際に操作する画面を作ります。デザイン通りに見た目を整え、ボタンをクリックしたときの動作などを実装します。
最近では、React、Vue.js、Angularなどのフレームワークを使うことが多く、より効率的に複雑な画面を構築できます。フリーランスとして「フロントエンドエンジニア」として参画する場合、この部分を専門的に担当します。
バックエンド開発
データベースへの保存や取得、ログイン認証、外部APIとの連携など、画面からは見えない処理を実装します。
Python(Django、Flask)、JavaScript(Node.js)、Ruby(Ruby on Rails)、PHP(Laravel)など、様々な言語とフレームワークが使われます。「バックエンドエンジニア」として参画する場合、サーバー側のロジックとデータ処理を担当します。
コード管理とバージョン管理
チームで開発する際は、Gitというツールを使ってコードを管理します。複数人が同時に作業しても、変更履歴を追跡でき、必要なら過去の状態に戻すこともできます。
GitHubやGitLabといったサービスを使うと、チームでコードを共有し、レビューし合いながら開発を進められます。フリーランスの案件では、Gitの基本操作(clone、add、commit、push、pull、merge)は必須スキルです。
開発環境のセットアップ
開発を始める前に、必要なツールや環境を整えます。
- エディタ/IDE VS Code、IntelliJ IDEA、WebStormなど、コードを書くためのツール
- ローカル開発環境 自分のパソコンで動作確認できる環境(XAMPP、Docker、仮想環境など)
- パッケージマネージャー npm、yarn、pipなど、必要なライブラリを管理するツール
- デバッグツール ブラウザの開発者ツール、ログ出力など、問題を見つけるための道具
フリーランスとして案件に参画する際は、クライアントの開発環境に合わせるため、セットアップ手順書に従って環境を構築することが多いです。
GitHub CopilotやCursor、Windsurf Editorなどのコーディング支援AIを使うと、コードの自動補完やバグ修正の提案を受けながら開発できます。「ユーザー登録機能を実装したい」と伝えれば、必要なコードを提案してくれます。
テスト:動作確認とバグ修正
コードを書いたら、それが正しく動くかを確認する必要があります。この段階では、様々なテストを行い、問題があれば修正します。
テストの種類と範囲
- 単体テスト(ユニットテスト)
- 個別の関数やメソッドが正しく動くかを確認します。開発者が必ず書くべきテストです。
- 結合テスト(インテグレーションテスト)
- 複数の機能を組み合わせたときに正しく動くかを確認します。
- システムテスト
- システム全体が要件通りに動くかを確認します。QAチームが担当することもあります。
- 受入テスト
- クライアントや実際のユーザーに使ってもらい、期待通りかを確認します。
フリーランスとして参画する場合、単体テスト〜結合テストの範囲を担当することがほとんどです。
手動テストと自動テスト
テストには、実際に画面を操作する手動テストと、プログラムで自動化する自動テストがあります。
手動テストはUIの見た目や操作性など、人間の判断が必要な部分を確認します。一方、自動テストはテストコードを書くことで、ボタン一つで何百ものテストケースを数秒で実行できます。
よく使うテストツール
実際の開発では、以下のようなテストツールを使います。
- Jest / Vitest JavaScriptの単体テストフレームワーク
- Cypress / Playwright ブラウザ上での動作を自動テスト
- pytest Pythonのテストフレームワーク
- Postman API通信のテスト
テストで見つかったバグは、優先度をつけて修正していきます。重大な問題から順に対応し、納期とのバランスを見ながら進めます。
AIにコードを渡して「このコードのテストケースを作成してください」と依頼すると、想定される入力パターンと期待される出力を含むテストコードを生成してくれます。バグの原因特定やエッジケースの発見にも活用できます。
公開・運用:世界に届ける
テストが完了したら、いよいよアプリを本番環境に公開します。しかし、公開して終わりではありません。運用段階では、ユーザーからのフィードバックを受けて改善を続けます。
公開と運用の流れ
- デプロイ準備
- サーバー環境の構築、ドメインの設定、SSL証明書の取得など
- 本番リリース
- テスト環境から本番環境へコードを移行
- 監視
- アプリの動作状況、エラー、パフォーマンスを常に確認
- 保守
- バグ修正、セキュリティアップデート、機能追加などの継続的な改善
継続的な改善サイクル
アプリを公開した後は、公開→監視・分析→フィードバック→改善という4つのステップを繰り返しながら、サービスを成長させていきます。
ユーザーの利用状況を分析し、問題点を発見したら改善し、再びリリースする。このサイクルを回し続けることで、より良いサービスへと進化していくのです。
改善サイクル
個人開発で全工程を経験する重要性
個人開発で学べること
個人開発では、フリーランスの案件では経験しにくい部分を補うことができます。
- 企画力 自分でアプリのコンセプトを考え、必要な機能を洗い出す経験
- 設計力 外部設計から内部設計まで、全体の構成を自分で決める経験
- 問題解決力 誰も答えを教えてくれない環境で、自分で調べて解決する力
- 完走力 企画から公開まで、最後までやり遂げる力
- ポートフォリオ 自分のスキルを証明する作品として、営業活動に活用できる
最初の個人開発プロジェクトの始め方
個人開発を始めるときは、以下のステップで進めると良いでしょう。
- テーマを決める
- 自分が日常的に使いたいと思うものを選ぶ。学習用なら、ToDoリスト、天気アプリ、簡単なブログなどがおすすめ
- 紙に書き出す
- 必要な機能を箇条書きにする。画面の構成も簡単にスケッチしてみる
- 技術を選ぶ
- 学びたい技術と、自分の現在のスキルレベルに合った技術を組み合わせる
- 小さく始める
- 最初は最小限の機能だけで動くものを作る。後から機能追加していけばいい
- 公開する
- GitHub Pagesやネットlifyなど、無料で使えるサービスで公開してみる
「初心者向けの個人開発プロジェクトのアイデアを5つ提案してください。それぞれ必要な技術と難易度も教えてください」とAIに聞けば、自分のレベルに合ったプロジェクト候補を提案してくれます。企画の壁打ち相手としても優秀です。
チーム開発で大切なこと
フリーランスとして働く場合でも、多くのプロジェクトではチームの一員として開発に参加します。個人開発とは違い、他のメンバーと協力しながら進める必要があります。
チーム開発で意識すべきポイント
- コミュニケーション 進捗報告、質問、問題の共有など、適切なタイミングで適切な相手に情報を伝える
- コードレビュー お互いのコードをレビューし合うことで、バグの早期発見やコード品質の向上につながる
- ドキュメント作成 設計書や仕様書、コメントなど、必要な情報を残して、チーム内での情報共有をスムーズにする
- バージョン管理 GitやGitHubを使って、複数人での開発を効率的に進める
個人開発で基礎を固め、チーム開発で協働スキルを磨く。この両方を経験することで、フリーランスとして活躍できる実力が身についていきます。
どうやってスキルを身につけるか
まずは興味のある分野を見つけよう
開発の流れを理解したら、次は自分がどの分野を学びたいかを考えることが大切です。
前のレッスンで学んだように、エンジニアの世界には大きく分けて以下の分野があります。
- フロントエンド開発 ユーザーが見る画面を作る。HTML、CSS、JavaScriptを使って、美しく使いやすい画面を実装
- バックエンド開発 サーバー側の処理を担当。データベース、API、認証など、画面から見えない部分を実装
- AI・データ分析 機械学習やデータ分析を活用して、インテリジェントな機能を実装
学習方法は大きく3つ
興味のある分野が見つかったら、次は学習方法を選びます。大きく分けて3つのアプローチがあります。
- AI活用による効率的な学習
- ChatGPT、Claude、Geminiなど学習支援AIを活用し、分からないことをその場で解決しながら学ぶ方法
- オンライン学習とコミュニティ
- 学習サイトや動画、コミュニティを活用して、自分のペースで学びながら仲間とつながる方法
- スクールで学ぶ
- 独学が難しい場合、プロの講師に教わりながら体系的に学ぶ方法
この章で学ぶこと
この章では、以下の順番で学習方法を解説していきます。
- フロントエンド開発の学習方法
- HTML、CSS、JavaScript、フレームワークの効率的な学び方
- バックエンド開発の学習方法
- サーバーサイド言語、データベース、APIの効率的な学び方
- AI・データ分析の学習方法
- Python、機械学習、データ分析の効率的な学び方
- AIを使った効率的な学び方
- ChatGPT、Claude、Geminiなどを活用した学習支援の具体的な方法
- オンライン学習サイトとコミュニティ
- 学習サイト、動画、コミュニティの活用方法と続け方のコツ
- 独学が難しいならスクールで学ぶ
- スクールに向いている人の特徴と、選び方・通い方のポイント
- 「つくる」だけじゃない!考える力を育てよう
- なぜ動くのかを理解し、問題を発見する思考法
最初から完璧を目指す必要はありません。まずは興味のある分野を一つ選んで、基礎から始めましょう。次のレッスンからは、各分野の具体的な学習方法と、AI時代ならではの効率的な学び方を詳しく解説していきます。
まとめ
- 5つの基本ステップ 企画・要件定義→設計→開発→テスト→公開・運用という流れを理解する
- フリーランスの関わり方 内部設計〜開発・テストを担当することが多く、企画や外部設計にはほとんど関わらない
- 個人開発の重要性 全工程を経験できる唯一の機会。小さく始めて完成させることを優先
- 外部設計と内部設計 システム全体の構成を決める外部設計と、実装の詳細を決める内部設計の違いを把握
- フロントエンドとバックエンド 画面側の開発と、サーバー側の開発の役割分担を理解
- テストの重要性 動くコードとテストコードをセットで納品するのがプロの仕事
- 継続的改善 公開後も監視・分析→フィードバック→改善のサイクルを回し続ける
- チーム開発スキル コミュニケーション、コードレビュー、ドキュメント作成、バージョン管理が重要
- 学習方法は次のレッスンで AI活用、オンライン学習、スクールなど具体的な学び方はこれから解説
次のレッスンでは、AIを使った効率的な学習方法を詳しく学んでいきます。