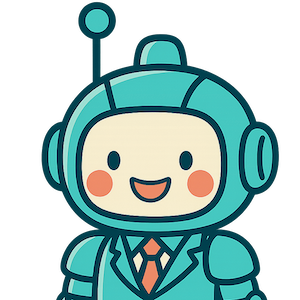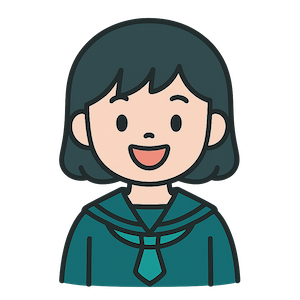入れ子リストの基本
入れ子のリストは、通常のリスト項目(<li>)の中に、新しいリスト(<ul>や<ol>)を配置することで作成します。これにより、情報を階層的に整理できます。
<li>大項目1
<ul> ← 子リスト
<li>小項目1</li>
<li>小項目2</li>
</ul>
</li>
<li>大項目2</li>
</ul>
で全体を囲む最上位
<ul>や<ol>を配置
インデントを調整
基本構造のポイントと作成ルール
入れ子リストを正しく作成するための重要なポイントと実装ルールを理解しましょう。
基本構造のポイント
- 親リスト(青色) 外側の
<ul>や<ol>で全体構造を囲む最上位のリスト - 子リスト(オレンジ色) 親の
<li>要素内に配置する入れ子のリスト(<ul>や<ol>) - 自動インデント ブラウザが階層レベルに応じて自動的にインデント調整
作成ルール
- 親のli内に配置 子リストは必ず親の
<li>要素の中に記述 - 同じタグの繰り返し
<ul>の中に<ul>、<ol>の中に<ol>が基本 - 混合も可能
<ul>の中に<ol>、<ol>の中に<ul>も可能 - 閉じタグの順序 内側から外側へ、正しい順序で閉じタグを配置
これらのポイントやルールを守ることで、ブラウザが正しく階層構造を認識し、適切なインデントで表示されます。
入れ子リストを試してみよう
以下のエディターで入れ子リストの基本的な書き方を試してみてください。
- 大項目と小項目の組み合わせを変更してみると、階層構造がより理解しやすくなります。
様々な入れ子パターン
パターン1:番号付きリストの入れ子
手順の中に詳細な手順がある場合は、<ol>の入れ子が効果的です。
パターン2:異なるリストタイプの組み合わせ
大分類は番号付き、詳細は箇条書きという使い分けも可能です。
パターン3:深い階層構造
3段階以上の深い階層も作成できますが、読みやすさを考慮して適度な深さに留めることが重要です。
入れ子は便利ですが、使いすぎると逆に分かりづらくなることもあります。以下の点に注意しましょう。
- 3段階以上の階層 視覚的に複雑になるため、実際のWebサイトでは慎重に使用しましょう
- 推奨される深さ 一般的には2〜3段階程度に留めることで、ユーザビリティを保てます
分かりやすい「入れ子リスト」を作る3つの原則
入れ子リストは便利ですが、ただ深くするだけでは逆に分かりにくくなります。 読み手にとって親切なリストを作るには、以下の3つの原則を意識するのが大切です。
原則1:論理的な階層にする
親子関係が直感的に分かるように、関連性の高い項目をグループ化しましょう。「大分類 → 中分類 → 小分類」のように、大きなテーマから具体的な項目へと掘り下げていくのが基本です。
- 良い例: 「家電」→「パソコン」→「ノートPC」
- 悪い例: 「家電」と「ノートPC」が同じ階層に混ざっている
原則2:階層を深くしすぎない
階層が深くなりすぎると、ユーザーは自分がどこにいるのか分からなくなってしまいます。多くのWebサイトでは、3階層までを一つの目安にしています。
- 推奨: 2〜3階層まで
- 注意: 4階層以上になると、多くの人が混乱し始めます
原則3:同じ階層のレベルを揃える
同じ階層には、同じレベル感の項目を並べましょう。例えば、「具体的な商品名」と「抽象的なカテゴリ名」が同じ階層に混ざっていると、構造が歪んで見えます。
- 良い例: 「ノートPC」「デスクトップPC」「キーボード」
- 悪い例: 「ノートPC」「デスクトップPC」「価格が安い順」
理解度チェッククイズ
入れ子リストミニクイズ
<ul>
<li>親項目1
<ul>
<li>子項目1</li>
<li>子項目2</li>
</ul>
</li>
<li>親項目2</li>
</ul><ol>
<li>手順1
<ul>
<li>詳細A</li>
<li>詳細B</li>
</ul>
</li>
<li>手順2</li>
</ol><ul>
<li>フルーツ
<ul>
<li>りんご</li>
<li>価格が安い順</li>
<li>みかん</li>
</ul>
</li>
</ul>まとめ
- 正しい構造 子リストは必ず親の
<li>要素内に配置 - 適度な深さ 一般的に3段階程度まで、最大4段階
- 論理的設計 関連性の高い項目をグループ化
- 一貫性の保持 同レベルの項目は同じ性質で統一
- 混合可能
<ul>と<ol>の組み合わせも自由に使用可能
次回は「定義リスト」について学習します。用語集やQ&A形式のコンテンツに最適な、特別なリスト形式を習得しましょう!